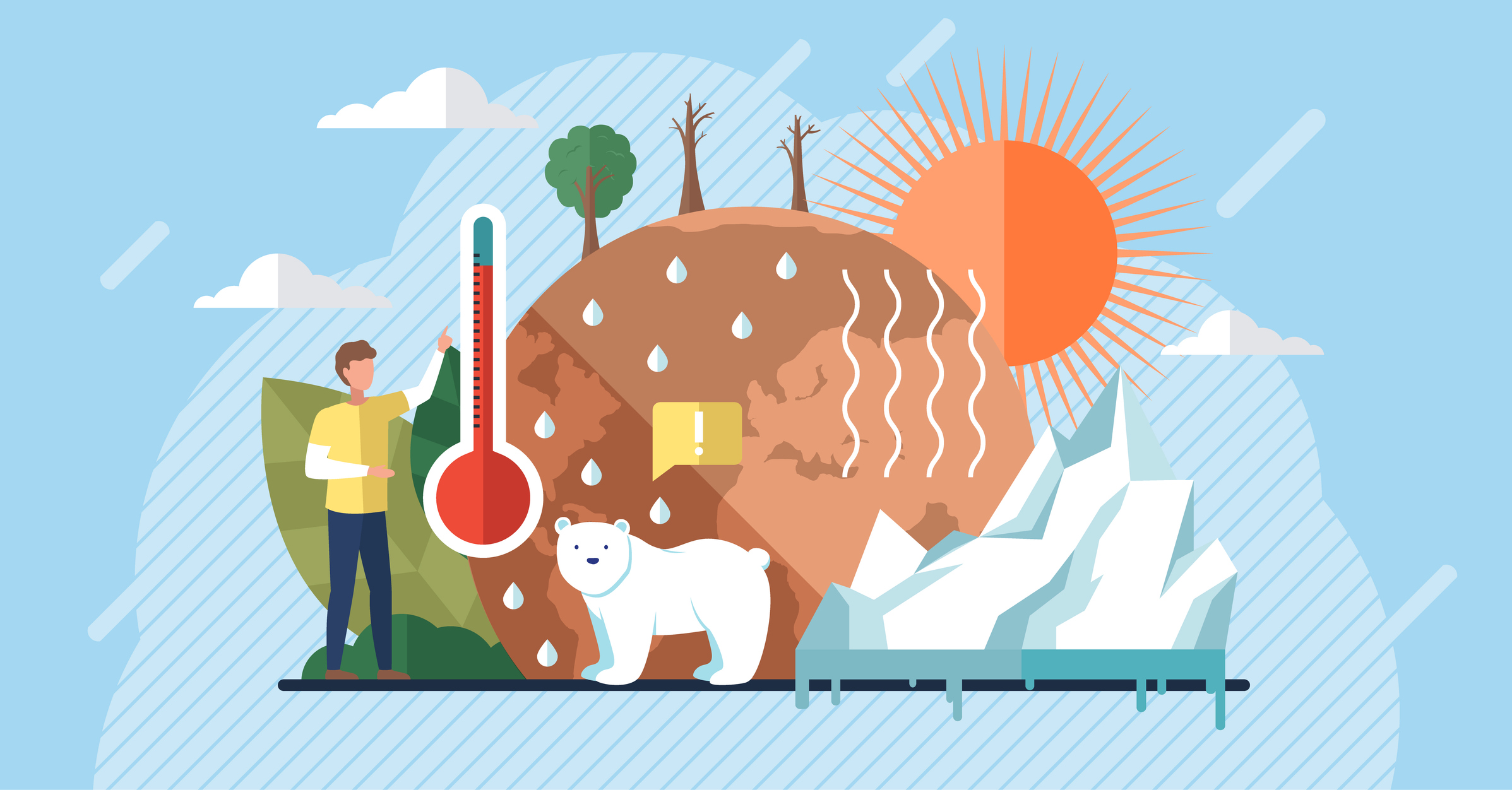エルニーニョ現象とは?仕組みを解説
エルニーニョ現象とは
エルニーニョ現象は、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて、海面の水温が平年よりも高くなり、その状態が1年程度続く現象です。
平常時は太平洋の熱帯域には貿易風と呼ばれる東風が常に吹いているため、海面付近の暖かい海水が太平洋の西側に吹き寄せられています。このため、海面の水温は太平洋赤道域の西側で高く、東部で低くなっています。海面の水温が高い太平洋西部では、海面からの蒸発が盛んになって、大気中に大量の水蒸気が供給されることから、上空で積乱雲が盛んに発生します。
それが、エルニーニョ現象が発生している時には、東風が平常時よりも弱くなり、西部に溜まっていた暖かい海水が東方へ広がるとともに、東部では冷たい水の湧き上がりが弱まります。このため、太平洋赤道域の中部から東部では、海面の水温が平常時よりも高くなるのです。積乱雲が発生する海域は平常時より東に移ります。
エルニーニョ現象とラニーニャ現象の違い
エルニーニョ現象とは逆に、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけての海面水温が低い状態が続く現象は、ラニーニャ現象と呼ばれています。
ラニーニャ現象が発生している時には、東風が平常時よりも強くなります。西部に暖かい海水がより厚く蓄積する一方、東部では冷たい水の湧き上がりが平常時よりも強くなります。このため、太平洋赤道域の中部から東部では海面水温が高くなります。
エルニーニョ現象とラニーニャ現象はそれぞれ数年おきに発生し、世界中の異常な天候の要因になり得ると考えられています。

エルニーニョ現象が日本に影響を及ぼすメカニズム
エルニーニョ現象とラニーニャ現象は、日本の天候にも影響を及ぼします。本稿では、エルニーニョ現象が日本に影響を及ぼすメカニズムについてみていきます。
エルニーニョ現象が発生すると、西太平洋熱帯域の海面水温が低下して、西太平洋熱帯域で積乱雲の活動が不活発になります。このため、日本付近では、夏季は太平洋高気圧の張り出しが弱くなるとともに、気温も低くなり、日照時間が少なくなるほか、西日本の日本海側では降水量が多くなる傾向があります。
また、冬季は、西高東低の冬型の気圧配置が弱まります。その結果、日本の気温は冬季としては高くなる傾向が見られます。
気象庁では、太平洋赤道域の中部から東部にある監視海域の平均気温が、1961年から1990年の平均海面水温である基準値を、6か月連続0.5℃上回る場合をエルニーニョ現象、0.5℃下回る場合をラニーニャ現象と定義しています。
エルニーニョ現象が電力需要に与える影響
エルニーニョ現象と2024年に史上最高を観測した世界平均気温の関係
2024年の世界平均気温が観測史上最高を記録したことをご存知でしょうか。実は、2023年も過去最高を記録していましたが、2024年はさらに記録を更新しました。
2024年の世界平均気温は、産業革命以前と比べて1.55℃上昇しています。2015年にフランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された、気候変動対策に関する国際的な枠組みのパリ協定では、世界の平均気温を産業革命以前と比べて2℃未満に抑え、できれば1.5℃未満に抑えることを目標にしています。それが1.5℃を上回ってしまいました。
この平均気温上昇の背景の一つとして、エルニーニョ現象の影響が考えられています。エルニーニョ現象は2023年春から発生していました。同年の冬には過去最高レベルにまで発達して、2024年の春頃まで続いたとみられています。
エルニーニョ現象は海に溜まっていた大量の熱を、大気に放出する現象でもあります。このため、大規模なエルニーニョ現象が起きると、地球全体の大気が温まり、気温が高くなります。大気への影響は、3か月から4か月ほど遅れて現れてくると言われています。
エルニーニョ現象と史上最高を観測した日本の2024年夏の平均気温
2024年春頃まで続いたエルニーニョ現象による大気への影響が、3か月から4か月遅れで現れた結果、日本の夏に記録的な高温をもたらしました。6月から8月にかけては、1946年の統計開始以来、西日本と沖縄・奄美で1位、東日本で1位タイの高温となりました。

さらに、9月から11月にかけての秋の平均気温も、過去最高を記録しました。その結果、年間の平均気温も、世界の平均気温と同様に2024年は統計開始以来最も高くなりました。平年を1.48 ℃上回り、これまで最高だった+1.29℃を大きく更新する結果となっています。
エルニーニョ現象と日本の電力需要への影響
エルニーニョ現象による高温は、日本国内での電力需要にも影響を及ぼします。国内の電力需給をエリアごとに想定し、検証している電力広域的運営推進機関によりますと、2024年度夏季の全国最大需要は、8月5日13時から14時の1億6095万kWでした。予備率は12.6%で、前年度並の高気温と電力需要を予想していたことから、電力の供給力は確保されました。一方で、北陸エリアと九州エリアでは想定を上回る需要が発生しました。
また、2024年度9月は、中旬過ぎまで8月並の高気温が続いたことから、北海道・東北・沖縄を除く7エリアで、需要が想定を超えました。エルニーニョ現象が原因と考えられる高温は、想定を上回る需要を発生させています。
エルニーニョ現象と企業のビジネスへの影響
エルニーニョ現象と電力料金への影響
エルニーニョ現象が起きた場合、電力料金の上昇が起きる可能性があるのは、水力発電への依存度が高い地域です。
資源エネルギー庁の2024年12月分の報告によると、日本国内の発電電力量の内訳は、最も割合が高いのが火力の78.2%、原子力が10.9%、風力や太陽光などの新エネルギーが8.3%、水力が7.0となっています。水力への依存度は高くないことから、日本国内の電気料金には影響はありません。
電力料金の上昇が起きる可能性があるのは、主にアジアの国々です。特に、ラオスやカンボジア、ミャンマーでは水力発電の割合が総発電量の5割以上を占めるなど大きく依存しています。エルニーニョ現象の影響で主要河川の水位が低下することで、流域に接する国は深刻な電力不足に直面する可能性があります。アジアの国々に進出している企業にとっては、エルニーニョ現象の発生状況には注意が必要です。

エルニーニョ現象と太陽光発電への影響
エルニーニョ現象が起きた場合、前述の通り夏季には太平洋高気圧の張り出しが弱くなり、気温が低く、日照時間が少なくなります。この影響によって、太陽光発電の発電量が減少することが考えられます。
また、西日本では降水量が多くなる傾向もあることから、この点からも太陽光発電の発電量減少が懸念されます。エルニーニョ現象の太陽光発電への影響は、主に夏季に出てくる可能性があります。
エルニーニョ現象のリスクに電力プラン変更で対応
脱炭素経営を目指して、太陽光発電の導入を検討している企業は少なくないと思います。ただ、自社で導入するケースで、夏季に需要が高まる業種の場合は、前述のようにエルニーニョ現象で夏季の発電量に影響が出る可能性もあります。
エルニーニョ現象の影響を気にすることなく、環境に配慮した電力利用を実現するのが、エバーグリーンの「CO₂フリープラン」です。電気に環境価値を保つ非化石証書を組み合わせることによって、実質的に再生可能エネルギーを提供しています。詳しくはこちらをご覧ください。